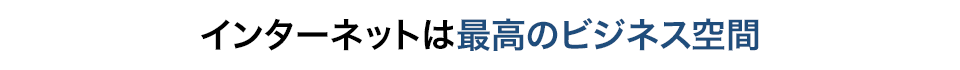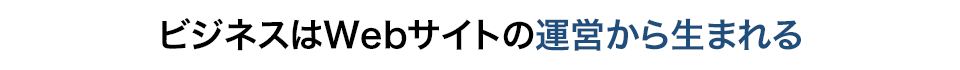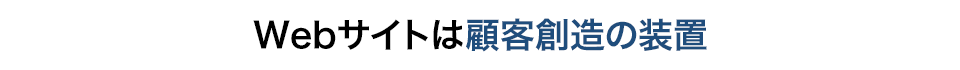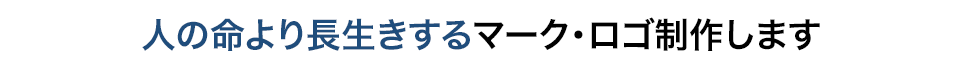Webマーケティングの時代へ
1億総インターネットWeb社会
生活者のデジタルシフト
グラフは約20年間のメディアの推移です。2000年代の始めまでメディアはTVを中心としたマスメディアの時代でした。2010年代になるとケータイが普及し始め、2015年には日本人の6割以上がスマホを持つようになり、PCからモバイルにシフトし、生活者は24時間どこからでも情報に接触でき発信できるようになります。
2022年にモバイルの試聴時間がTVの視聴時間を超え1日7.4時間のメディア視聴時間の中で、5.3時間はケータイなどのインターネット接続です。しかもTV視聴時間の中で50%以上はオンライン接続(YouTube・Netflix‥etc)というのが実情です。
人口以上にスマートフォンが存在するインターネット社会、5歳から79歳の日本人のうち既に95%もの方がスマートフォンを保有しています。個人はスマホを肌身離さず持ち、誰もがインターネット社会での一番の必需品は、スマホだと感じているはずです。
メディア総接触時間の推移

インターネットにより情報の流れが変わりマーケティングも変化
生活の情報源はマスメディアからインターネットへと変遷しました。マスメディア時代の情報発信は企業側からの一方向でしたが、インターネット社会では購入者も、24hどこからでも情報を発信できます。この双方向の情報発信の流れのなか、企業のマーケティングは大きな転機を迎えています。インターネットが出現し、メディアの分散化が始まり25年余り、シュリンクするマスメディアに頼っても、企業は生活者との双方向の情報の流れに対処できません。芸能人やコメンテーターは、これまでテレビなどのマスメディアに出演し自己をアピールしてきましたが、インターネット社会では自らがユーチューバーとなり情報を発信、オンラインプレゼンスを高めています。
インターネット社会、
Webマーケティングの基礎とは

リアルとインターネットで、企業マーケティングの展開を比べた場合、コスト、コミュニケーションツール、接触数、時間制約、利便性などのあらゆる点で、インターネットはリアルを超えたマーケティング空間だと言えます。さらにインターネット上のマーケティング施策はデータ化され効果検証が容易に行え、マーケティングを進化させることができます。しかし、多くの企業はインターネット環境でのマーケティングを十分にマネジメントできていないのが現状です。
インターネット社会、企業が事業を優位に進めるには、情報発信力のある自社メディア(オウンドメディア)を持ち、オンラインプレゼンスを高めることがWebマーケティングの基礎いえます。そのためにはGoogleの検索サービスで上位に表記されることです。Googleは各Webサイトの品質向上のため、サイト分析やインターネット上での検索状況が解明できる、様々な装置を無料で公開しています。企業はこれらの装置を活用し、自社Webサイトを改善できます。Googleが定める法則によりサイトを構築しGoogleから評価されれば、インターネット上で多くの潜在顧客と出会えるようになります。
インターネット社会のWebマーケティングのやり方
日本でのインターネット検索数は2兆回を越え、知りたいことについての80%は、インターネット検索で調べていると報告されています。このような状況において、企業は事業に関係する潜在顧客が知りたい情報を、自社のWebサイトに蓄積することが重要となります。
そして、その情報を検索上位に表記させ多くの潜在顧客を自社Webサイト(オウンドメディア)に導くインターネットスキルも必要となります。
自社Webサイトをマーケティングの核として機能させ、そのフィールドで潜在顧客と接触を繰り返し見込客へと導き、得られたデジタルデータでさらにマーケティングを進化させていく、このサイクルを経営に機能させることがインターネット社会のweb マーケティングの 基礎だとを考えます。

本物の商品やサービス、レアな情報を発見できる
インターネット社会の新たなビジネスシーン
現実の行動に即した情報を、いつでも検索でき、誰もが情報発信装置を持つインターネット社会は、これまでのビジネスの流れを大きく変えました。インターネットの出現までは、商品の宣伝は潤沢な広告費用を投じることができる大企業だけのものでしたが、インターネット社会では、個人や中小企業でも情報発信がおこなえます。たとえレアなサービス情報であっても、それを検索する人たちがいれば発見されるようになりました。
インターネット上のWebサイト情報を評価するGoogleの検索エンジンは、 検索されるキーワードに対して、おすすめできるサイト情報から順に表記します。 検索者は見つけたい情報が素早く検索でき、気になる商品やブランドは使った方の声まで確かめます。インターネット社会は本物の商品を持ちながら情報発信力に欠けていた中小企業や、需要が少ない商品の生産者にとって、新たなビジネスシーンの幕開けだといえます。